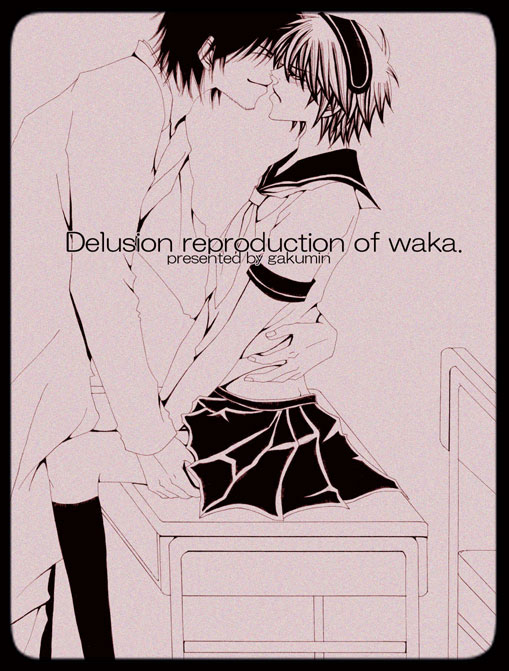
「お前、ガードが固いのか無防備なのかよく分からんなあ」
気がつくと、ひょいと抱え上げられ、机に座らされていた。
アキラは自分を他人に好きなように扱われるのは大嫌いだ。
今だって怒ってもいいのに、とそう思う。
なのに目の前にある暖かい色の目を見返すと、自然な感じにふっと
身体の力が抜けた。
「アンタ…好きなのか、その……」
自分を、と言い切れずに口ごもったアキラを見て、源泉は案外照れ
くさそうな顔つきになった。
「俺だって困ってるんだぞ、なんたって先生と生徒だしなあ。だが」
「……なに」
「もう決めた。お前は誰にも譲ってやらん。幼馴染くんにも、あの
イヤミな理事長にもな」
自惚れるな、と言いたいところだった。
この男はまだ自分の気持ちを一度も聞いてくれていない。
なのに、「分かってる」とでも言いたげな顔で、源泉はアキラの腰に
スルリと手を回した。
大きな手が制服を持ち上げ、素肌を撫でるのにビクッとしたが、
それでも逃げなかった。
(あ……キスされる)
望みが叶えられるのだと分かるから、逃げたりしない。
それが自分の告白になるのだろうと思い、アキラは目を閉じた。
周囲が誰かを好きだと騒ぐのを見ても、どんな気持ちか分から
なかった。
なのに、今はこの冴えない化学教師ばかりを見つめている自分が
いる。
(好き……なんだ、きっと。アンタのこと)
病気みたいに鼓動が速いのも。
目を閉じる前に見た、笑ったかたちの唇に触れたいと願うのも。
全部全部そのせいだ。
自分に触れる、源泉の大きな掌の熱を感じていた。
カーテンの隙間からもれる、オレンジ色の陽光に照らされる。
放課後のざわめきが外から響くのを、他人事のように聞きながら。
アキラはやがて自分に触れてくる甘い運命を、ひっそりと待ちわびた。